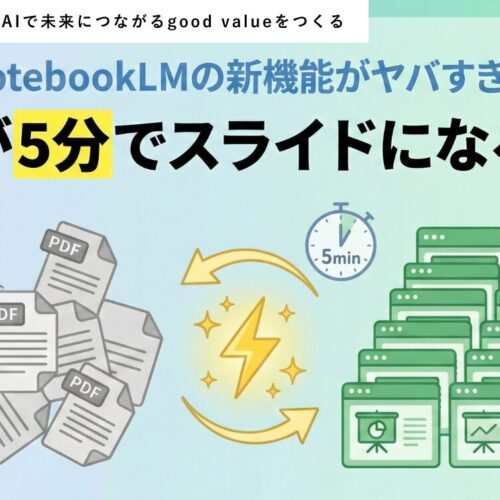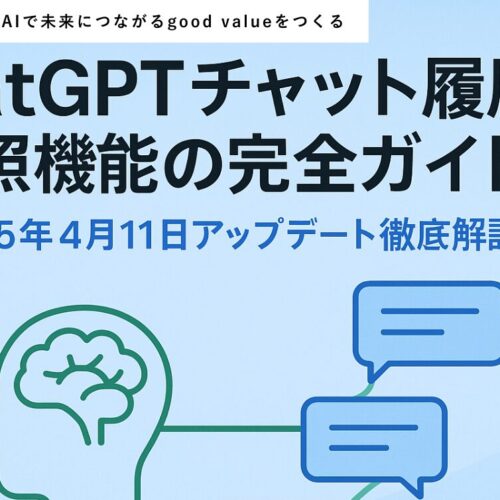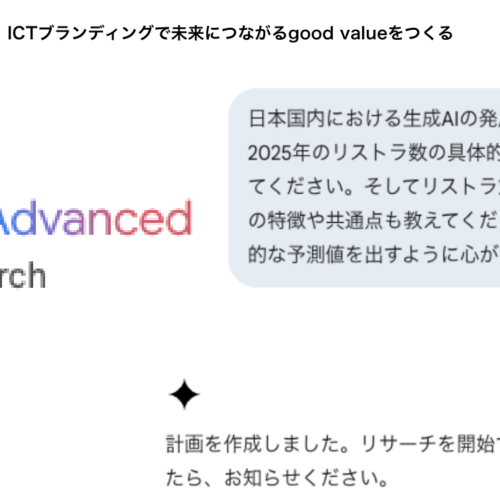【マジで焦る?】AIに仕事を奪われる前にやるべきたった3つのこと|消える5職種と生き残る戦略
公開日:2025年05月22日

代表取締役
貝出康

「ねえ、10年後もあなたの仕事、残ってると思う?」
この質問、職場のランチタイムや飲み会で最近よく耳にしませんか?AIやロボットの話題が飛び交う昨今、私たち多くのビジネスパーソンが密かに抱える不安かもしれません。コンビニの無人レジに慣れてきた頃、ふと「これって私の仕事も代わられるってこと?」と考えたことがある人も多いはず。
安心してください、完全に人間の仕事が消えるわけではありません。でも、変化は確実に起きています。この記事では、テクノロジーの波に乗り遅れないために今から準備できることをお伝えします。
10年後に消える可能性が高い5つの仕事
「まずは現実を直視しましょう」とよく言いますよね。ちょっと怖いかもしれませんが、テクノロジーに置き換わりやすい職種を知っておくことは大切です。
1. 接客業:スマイルの向こう側に無人レジ
皆さんも経験があるでしょう。スーパーで「いらっしゃいませ」と言ってくれるのが人からタッチパネルに変わり、「袋はご入用ですか?」という質問がスピーカーから流れる世界。無人レジの普及は、単に効率化というだけでなく、人手不足の解消という社会課題への対応でもあります。
でも、高級レストランやブティックでは、まだまだ人間の温かみが求められています。「お客様の表情を見て最適なワインを提案する」といった、微妙なニュアンスを読み取るサービスは、AIにはまだ難しいんです。
2. 採用業務:AIがあなたの履歴書を読んでいます
「履歴書を送ったけど、誰が読んでるんだろう?」実は、AIかもしれません。採用担当者が山のような応募書類をスクリーニングする時代は終わりつつあります。AIは数秒で何百もの履歴書をスキャンし、求める条件に合った候補者をピックアップできるんです。
ただし、「この人、うちの社風に合いそう」という直感や、面接での化学反応を感じ取るのは、まだ人間にしかできません。採用業務は「機械による選別」と「人間による最終判断」のハイブリッドになっていくでしょう。
3. 翻訳業務:AIは”言葉”を訳せても”心”は訳せない
「Google翻訳、最近めちゃくちゃ良くなってない?」と感じている方も多いはず。AIによる翻訳精度は日進月歩で向上しており、一般的なビジネス文書なら十分実用的なレベルに達しています。
ただし、皮肉やユーモア、文化的な背景が必要な翻訳は別です。「空気を読む」翻訳、例えばマーケティングコピーや文学作品は、まだまだ人間の感性が必要です。「訳す」から「伝える」へ。翻訳者の役割は変わっていくでしょう。
4. 経理:数字を追うのはAIに任せて
「領収書の仕分け、面倒くさい…」そんな声が聞こえてきそうな経理業務。データ入力や計算、定型的な報告書作成は、AIやRPAソフトウェアによって自動化が進んでいます。クラウド会計ソフトの進化は、経理担当者の日常業務を大きく変えました。
これからの経理担当者に求められるのは、数字の「入力者」ではなく「解釈者」としての役割です。「この数字の裏にある戦略は何か」「異常値の原因は何か」を読み解くスキルが重要になるでしょう。
5. アナウンサー:AIにはない”温かみ”を武器に
「次のニュースです」この言葉、実はAIが話しているかもしれません。音声合成技術の進化により、自然な抑揚や間を持った音声生成が可能になっています。定型的なニュース読み上げやナレーションは、徐々にAIに置き換わる可能性があります。
しかし、感情を込めた語り、視聴者との一体感、予想外の出来事への対応など、「生きた放送」の醍醐味は人間ならでは。テクノロジーが進化するほど、逆に「人間らしさ」の価値が高まるかもしれませんね。
AIが苦手なこと、人間だからこそできること
ここまで読んで「やばい、私の仕事も危ない?」と思った方もいるかもしれません。でも、AIには決定的な弱点があります。それは何でしょうか?
AIは「融通の利かない優等生」
AIって「一点集中型の優等生」みたいなものです。与えられた目標だけを見つめて突き進むのは超得意。でも、急に「ちょっと方針変えようか」と言われると途端に混乱します。皆さんの職場にもいそうな「融通の利かない真面目くん」をイメージするとわかりやすいかも(笑)
例えば、チェスAIは「勝つこと」だけを目標に学習します。でも中盤で「実は引き分けを目指してね」と言われても対応できません。一方、人間は状況に応じて目標を切り替えたり、複数の目標をバランスよく追求したりするのが得意なんです。
人間の強み:創造力、課題発見力、そして「体験」
「誰にも思いつかなかったアイデア」を生み出すのは、まだまだ人間の特権です。AIは過去のデータから学習するので、全く新しい発想をするのは苦手。例えば「宅配ピザとサブスクリプションを掛け合わせたら面白いんじゃない?」といった異分野の掛け合わせは、人間の創造力の賜物です。
また「そもそも何が問題なのか」を見つける課題発見力も人間の強みです。AIは与えられた問題を解くのは得意ですが、問題自体を発見するのは苦手。例えば「なんでこの商品、若い女性に売れないんだろう?」という問いを立てるのは人間の役割です。
そして何より、「実体験に基づく言葉」の重みは、AIにはまだ真似できません。「私も同じ経験をしました」という上司の一言が新入社員の心を動かすように、体験から紡ぎ出される言葉には特別な力があるのです。
ビジネスパーソンが今から磨くべき3つのスキル
さて、これからのAI時代を生き抜くために、私たちはどんなスキルを磨くべきでしょうか?
1. 課題を創造する力:「問い」を立てる人が価値を生む
「答え」を出すのはAIに任せて、「問い」を立てるのは人間の仕事—これがAI時代の分業になるでしょう。「なぜ?」を繰り返し問いかけ、本質的な課題を見つける力が重要です。
例えば、「売上が下がっている」という状況に対して、単に「どうやって売上を上げるか」と考えるのではなく、「そもそも顧客が求めているものは変わったのではないか」「新しい販売チャネルを作るべきではないか」という問いを立てられるかどうかが勝負です。
今日からできること:日常の中で「なぜ?」を3回繰り返す習慣をつけましょう。最初の「なぜ」で止まらず、さらに深掘りすることで、思考の筋肉が鍛えられます。
2. 一次情報収集力:現場の「肌感覚」がデータより価値になる
AIが処理できるのは、すでにデジタル化されたデータだけ。まだデータになっていない「現場の空気感」「顧客の表情」「取引先との雑談で得た情報」などは、人間にしか収集できません。
例えば、アパレル業界で「この生地、触り心地がいいね」と思わず口にした顧客の一言や、飲食店で「ちょっと塩辛いかな」とつぶやいた瞬間の表情など、デジタルデータにはなりにくい情報こそ、競争優位の源泉になります。
今日からできること:週に一度は「現場」に出る時間を作りましょう。オフィスワークが中心の方は、実際に店舗や工場に足を運んだり、顧客と直接会ったりする機会を意識的に増やしてみてください。
3. 人間関係構築力:「信頼」は最強の差別化要因
AIがどれだけ進化しても、「あの人だから話を聞きたい」「あの人だから仕事を任せたい」という信頼関係は簡単には作れません。異文化間のコミュニケーションや、微妙なニュアンスの交渉など、人間関係の構築は依然として人間の領域です。
特に「難しい話を切り出す」「反対意見を伝える」「チームの士気を高める」といった繊細なコミュニケーションは、AIにはまだまだ難しい領域です。
今日からできること:毎週1人、これまであまり話したことがない同僚とランチに行ってみましょう。あるいは、社外の勉強会やイベントに参加して、異なる業界の人との接点を作ってみてください。
AIとの共存:これからの働き方のヒント
「AIvs人間」ではなく「AI×人間」の発想で考えてみましょう。AIが得意な「効率化」と人間が得意な「創造性」を掛け合わせると、新しい可能性が見えてきます。
AIを「パワーツール」として使いこなす
かつて電卓が登場したとき、「計算ができなくなる」と心配する声がありました。しかし実際には、電卓のおかげで複雑な計算に時間を取られずに済み、より創造的な思考に時間を使えるようになりました。
AIも同じです。例えば、マーケティング担当者なら「データ分析はAIに任せて、その結果からクリエイティブな施策を考える」といった使い方ができます。AIを「代替者」ではなく「パワーアップツール」と捉えることが大切です。
「人間らしさ」こそが最大の武器になる時代
皮肉なことに、テクノロジーが発達するほど「人間らしさ」の価値が高まります。共感力、創造性、倫理的判断、文脈理解など、AIが苦手とする領域こそ、これからのビジネスパーソンが磨くべきポイントです。
例えば、オンライン会議が当たり前になった今だからこそ、「直接会って話す価値」が再評価されています。テクノロジーが進化するからこそ、人間にしかできない「温かみのあるコミュニケーション」の価値が高まるのです。
さあ、明日からあなたにできること
テクノロジーの波は確実に来ています。でも大丈夫、今日からこの3つを始めれば、その波に乗ることができます
- 毎日15分、異分野の本や記事を読む(創造力アップ!)
- 「なぜ?」を3回繰り返す習慣をつける(課題発見力の訓練)
- 週に1人、新しい人とコーヒーを飲む(人間関係構築の練習)
AIが発達する未来は、実は人間らしさがもっと輝く時代かもしれません。あなたにしかできないこと、あなただからこそ言える言葉を大切にしていきましょう。
当社サイトでは他にもビジネスに役立つ情報を発信しています。ぜひ、他記事もチェックしてくださいね。
無料相談受付中
AI技術の導入や活用方法について相談したい方は、株式会社カンマンにお問い合わせください。
最新のAI技術を活用した経営戦略や業務効率化について、無料でご相談を承っております。
AIの無料セミナー優先参加特典や最新情報が受け取れます
【無料】AIメルマガを受け取る

代表取締役
貝出康
1963年徳島市生まれ。 1999年に楽天の三木谷社長の講演を聴き、イン ターネット時代の到来を悟る。翌年、ホームペ ージ制作会社カンマン設立に参画し、これまで のキャリアで培った営業や人事のスキルを活か しての顧客開拓や社内・労務管理を実践。2019 年〜代表取締役。