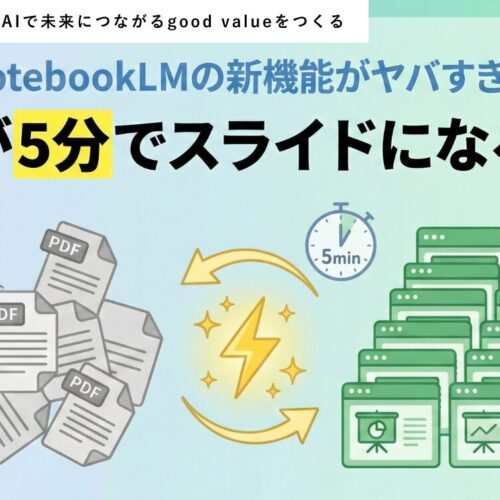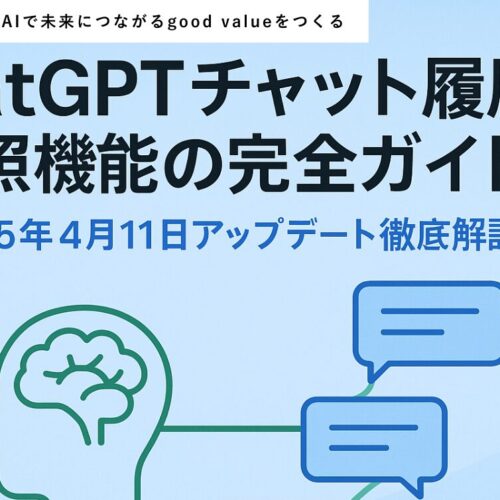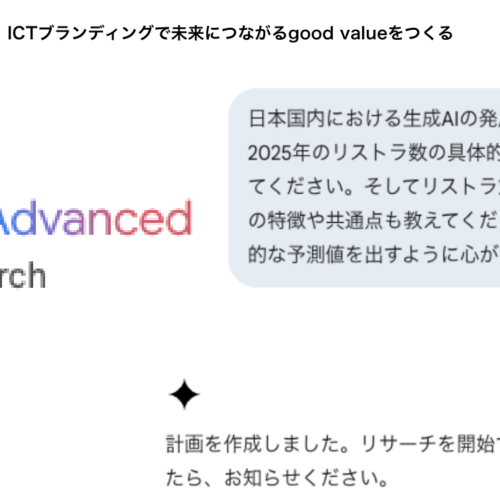AI導入時のセキュリティ対策8のチェックリスト
公開日:2025年03月24日

Webディレクター兼エンジニア
田中健介

近年、AI(人工知能)技術の発展により、多くの企業が業務効率化や生産性向上を目的にAIツールを導入しています。しかし、AIを安全に活用するためには、適切なセキュリティ対策が必要不可欠です。特に中小企業は、大企業に比べて情報セキュリティの対策が手薄になりがちです。
本記事では、AI活用を考える中小企業経営者の方に向けて、実践すべきAIセキュリティ対策を8項目のチェックリスト形式で解説します。御社のAI運用が安全かどうか、ぜひチェックしてみてください。
AIツール提供元の信頼性を確認する
導入するAIツールが信頼できる企業によって運営されているかを確認しましょう。プライバシーポリシーやデータの取り扱いが明確でない場合、情報漏えいのリスクが高まります。以下のポイントをチェックしてください。
- 提供企業の実績や評判を調査
- プライバシーポリシーの内容を確認
- データの取り扱い方針を把握
特に、機密情報を扱う場合は、海外のAIツールの利用には慎重になるべきです。
モデルのトレーニング設定をオフにする
一部のAIツールでは、入力したデータを今後のAI学習に活用する設定(トレーニングモード)がデフォルトでオンになっている場合があります。この機能をオフにすることで、自社のデータが第三者に利用されるリスクを軽減できます。
個人情報や機密情報をAIに入力しない
AIに入力したデータは、システムの学習データとして蓄積される可能性があります。例えば、氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報などの個人情報や機密情報を入力しないようにしましょう。
また、AIが生成した内容をそのまま顧客や社内で使用しないことも重要です。特に、ビジネスの意思決定に関わる内容は、必ず人間がチェックし、慎重に取り扱いましょう。
AIが生成した内容を必ず確認する
AIは便利なツールですが、間違った情報を生成することもあります。そのため、生成された内容を鵜呑みにせず、誤った情報や機密情報が含まれていないか必ずチェックする習慣をつけましょう。
特に、契約書、財務報告、プレスリリースなどの重要書類の作成には慎重な確認が必要です。
最新のアップデートを適用する
AIツールは定期的にアップデートされます。セキュリティの脆弱性が発見されると、すぐに修正パッチが提供されるため、常に最新バージョンに更新することが重要です。
古いバージョンのツールを使い続けることは、ハッキングや情報漏えいのリスクを高める要因になるため、社内で定期的にアップデート状況を確認する仕組みを作りましょう。
2段階認証(多要素認証)と強力なパスワードを設定する
AIツールのアカウントが不正にアクセスされることを防ぐために、2段階認証を有効にしましょう。特にクラウド型のAIツールを利用する場合、不正アクセスのリスクを減らすためにワンタイムパスワード(OTP)や生体認証を活用するのがおすすめです。
また、「123456」「password」といった単純なパスワードではなく、英数字・記号を組み合わせた強力なパスワードを設定し、定期的に変更することが重要です。
利用履歴・データ削除の方法を把握する
AIツールに入力したデータは、サービス提供者によって保持される場合があります。そのため、データ削除の方法を事前に確認し、不必要なデータは適切に削除することが大切です。
特に、顧客情報や機密情報を扱う場合、データ保持期間や削除方法を把握し、定期的にクリーニングを行うことをおすすめします。
公共のWi-FiではAIを使用しない
フリーWi-Fiは便利ですが、セキュリティリスクが高く、データが傍受される危険があります。AIツールを使用する際は、VPNを活用するか、信頼できるネットワークを使用しましょう。
まとめ:AIを安全に活用するために
AIは業務の効率化を大幅に向上させる強力なツールですが、その利便性と引き換えにセキュリティリスクも存在します。特に中小企業は、大企業に比べて専任のセキュリティ担当者を置くのが難しいため、基本的なセキュリティ対策を徹底することが重要です。
今回ご紹介した8項目のチェックリストを活用し、自社のAI活用における安全性を向上させましょう。
AIの力を最大限活用しながら、セキュリティ対策を万全に整えてください!
AIの無料セミナー優先参加特典や最新情報が受け取れます
【無料】AIメルマガを受け取る

Webディレクター兼エンジニア
田中健介
2023年に株式会社カンマンへ入社。
フロントエンジニアとしてサイト構築に携わった後、Webディレクターとして様々な案件に携わる。
また、専門学校の非常勤講師としても活動。