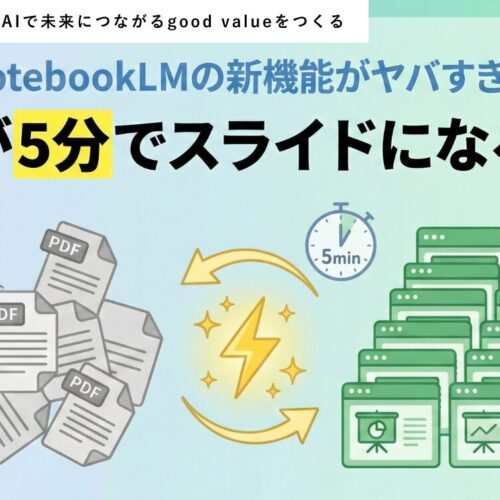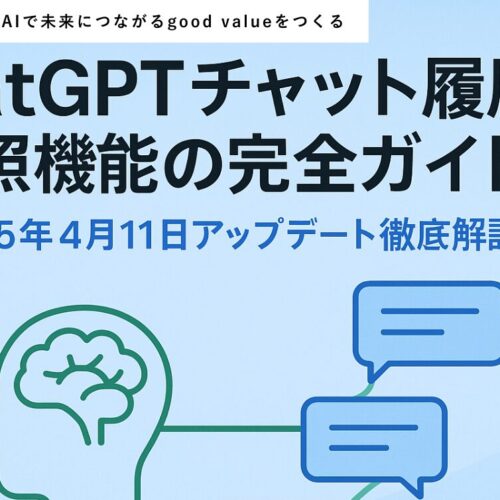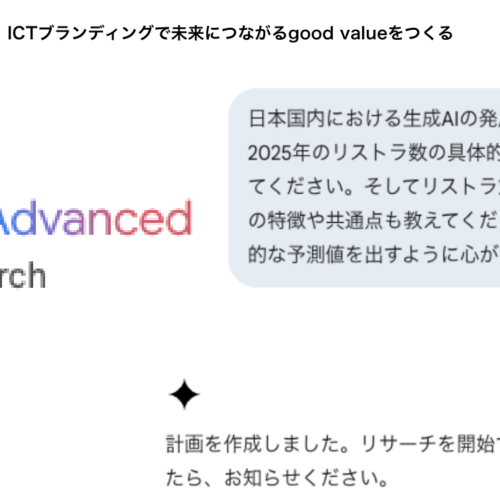知られざるAIの裏側:学習モデルの“闇”を知る
公開日:2025年07月31日

デザイナー
横田 佳恵

「AIは公平で、論理的な判断をしてくれる」
そんなイメージを抱いている方は少なくないかもしれません。しかし、実際にはAIの判断の背後には、私たちが想像するよりも“人間的”な要素が潜んでいます。
なぜなら、AIの「賢さ」はすべて“人間が与えたデータ”によって作られているからです。
本記事では、AI開発の裏側にある 学習データの偏り や 倫理的課題 について掘り下げ、私たちがAIと付き合う上で気をつけるべきポイントを考えます。
「学習データ」はどこから来ている?
AIは「学習する」ことで機能しますが、その学習には膨大なデータが必要です。現在主流の大規模言語モデル(LLM)は、以下のような情報を材料にしています。
- インターネット上の公開テキスト(Wikipedia、ブログ、ニュース記事など)
- 書籍(著作権切れのものや許諾済みのデータ)
- SNS投稿、QAサイトのやりとり
ここで重要なのは、インターネットは“偏った世界”であるという事実です。
特定の文化や言語が多く含まれ、少数派の意見や地域の事情が反映されにくいのです。
偏りは「差別」を生むかもしれない
例えばあるAIが採用選考に使われるとします。
過去のデータをもとに「優秀な人材」の傾向を学習した結果、次のような偏りが生まれる可能性があります。
- 男性ばかりが採用されていた過去 → 女性候補者が不利に
- 都市圏出身者が多かった → 地方出身者が過小評価される
このような偏りはAIが意図的に差別をしているわけではありません。
人間の過去の行動や判断が、データとしてAIにそのまま継承されているのです。
「著作権」と「プライバシー」の問題も
生成AIが学習した内容の中には、著作権がある文章や画像が含まれていることがあります。
クリエイターの作品が無断で学習に使われることへの反発が強まっており、訴訟に発展した事例もあります。
また、個人のSNS投稿や検索履歴などが含まれる場合、プライバシー侵害のリスクも指摘されています。
生成された内容に特定個人の情報が“混入”してしまう事例も報告されています。
私たちができる「向き合い方」
AIを使う上で重要なのは、「AIは万能ではない」という前提を忘れないことです。
- AIの回答や判断は 参考のひとつにすぎない と認識する
- 学習元のデータにある 偏見や過去の構造 を疑う視点を持つ
- プロジェクトでAIを使う際は 透明性と説明責任 を意識する
これからの社会では、AIを使う側の倫理観こそが問われる時代になっていくでしょう。
おわりに
AIは確かに便利でパワフルなツールです。
しかし、その判断の根拠や背景には、必ず“人間由来のもの”が存在しています。
「知らないまま使う」のではなく、「仕組みを知ったうえで使う」。
これが、これからの時代のAIとの付き合い方の第一歩になるのではないでしょうか。
AIの無料セミナー優先参加特典や最新情報が受け取れます
【無料】AIメルマガを受け取る

デザイナー
横田 佳恵
株式会社カンマン、制作課デザイナー。
2018年入社。主にウェブデザイン領域や75案件以上の幅広い保守対応、SNS運営、ウェブサイトコーディングなどを担当。