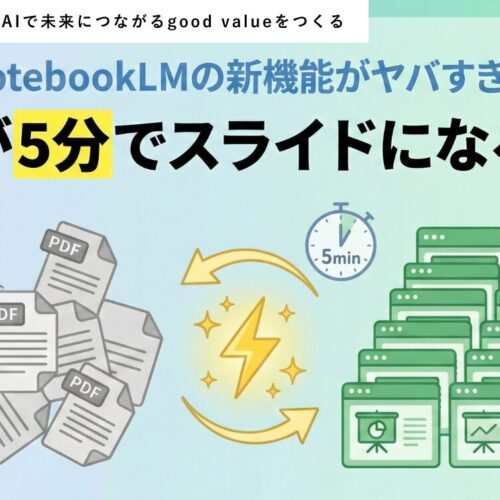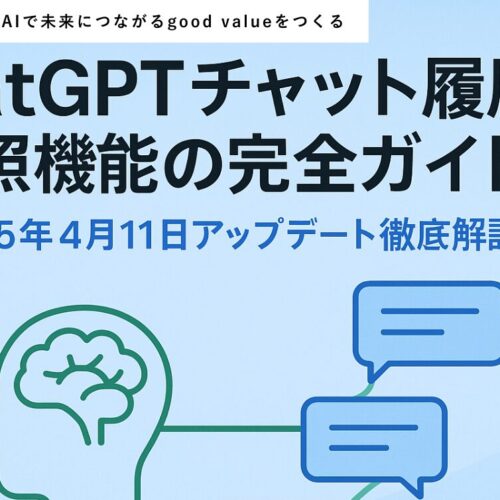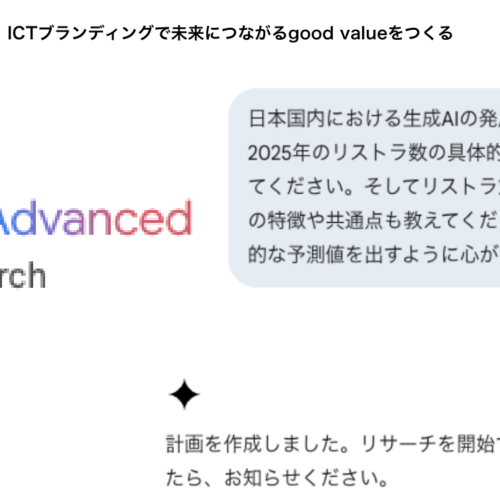AIっぽくない文章を書くのコツ5選
更新日:2025年03月24日
公開日:2025年03月21日

Webディレクター兼エンジニア
田中健介
AIツールを使って文章を書くことは今や当たり前になっていますが、その文章が「機械的」に感じられてしまうと効果半減です。AI生成コンテンツを人間味あふれるものに変える実践的なアプローチをご紹介します。
生きた体験を織り込む

AIは膨大なデータから文章を生成するため、どうしても一般論や抽象的な表現になりがち。これを解決するには、具体的な経験談やリアルなエピソードを盛り込むよう指示することが効果的です。
「先日山中湖でキャンプした時、朝もやの中から見えた富士山の姿は今でも目に焼き付いています。テントの中で飲んだ熱いコーヒーの香りと共に、あの静けさは都会では味わえない贅沢でした」
このように五感を刺激する表現を入れることで、読者はその場にいるような臨場感を体験できます。
表現のバリエーションを豊かに

AIの文章はしばしば同じような語彙や文体のパターンが繰り返されます。これを避けるためには、同じ意味でも様々な言い回しを使ったり、あえて少し個性的な表現を取り入れるよう指示しましょう。
「この商品は非常に優れています。使いやすく、機能性も高いです。さらに価格も適切です」より、「手にした瞬間からその絶妙な使い心地に驚かされる。複雑な機能がこんなにシンプルに収まっているのが嬉しい。それなのにこの価格帯というのだから、財布に優しいのも見逃せないポイントだ」の方が読みたくなりませんか?
感情表現を大切に

情報提供に終始しがちなAIの文章に「人間らしさ」を加えるなら、感情表現は欠かせません。喜怒哀楽や戸惑い、安堵といった感情を適度に盛り込むことで、文章に温かみが生まれます。
「新しいプロジェクトが始まった時は正直不安でいっぱいでした。でも仲間と乗り越えた瞬間の達成感は何物にも代えがたく、思わず笑みがこぼれました」
このような感情移入できる表現があると、読者は「本当に経験した人の声」として受け取ります。
ストーリー性を持たせる

単なる情報の羅列ではなく、導入・展開・結論といった流れを意識した構成にすることで、読者を引き込むことができます。
「昨夜、久しぶりに学生時代の友人から連絡が来た。実は彼が起業し、新しいサービスをリリースするという。話を聞けば聞くほど興味が湧き、気づけば私も協力を申し出ていた。こうして予想外の新しい挑戦が始まることになったのだ」
適度な脱線を恐れない

完璧に整理された文章は、時として無機質に感じられます。適度な余談や個人的な見解を挟むことで、文章に人間味が増します。
「データ分析の重要性については多くの専門家が指摘していますが、私自身、エクセルと格闘した学生時代の苦い記憶があり、今でも複雑な関数を見ると身構えてしまいます(笑)。でも、そんな私でも最近のAIツールなら直感的に使えるようになっているんですよね」
このように、あえて本筋から少し外れた話を入れることで、親しみやすさが生まれます。
AIツールは私たちの強力な味方ですが、最終的に読者の心に届く文章にするには、こうした「人間らしさ」を意識的に取り入れることが大切です。技術と感性を融合させて、より魅力的なコンテンツを生み出していきましょう。
【まとめ】AIと人間性の融合こそが鍵
AIは私たちのコンテンツ作成を効率化する素晴らしいツールですが、真に読者の心に響く文章にするためには、上記で紹介した「人間らしさ」のエッセンスが不可欠です。具体的な体験、多様な表現、感情の機微、物語性、そして適度な脱線—これらを意識的に取り入れることで、AI生成文章の質は格段に向上します。
最終的には、技術の効率性と人間の感性を絶妙にブレンドすることが、オンラインコンテンツが溢れる時代において、あなたの文章を際立たせる決め手となるでしょう。AIを使いこなしながらも、その向こう側にある「人間らしさ」を大切にする姿勢が、読者との深い共感と信頼関係を築く基盤となるのです。
AIの無料セミナー優先参加特典や最新情報が受け取れます
【無料】AIメルマガを受け取る

Webディレクター兼エンジニア
田中健介
2023年に株式会社カンマンへ入社。
フロントエンジニアとしてサイト構築に携わった後、Webディレクターとして様々な案件に携わる。
また、専門学校の非常勤講師としても活動。